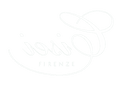Cisei ショールーム開設
ブランドを立上げて15年が過ぎました。あきらかに流行りや時代は変わり、特にここ2年は色々な意味で大きな変化ばかりの時間となっているかと思います。仕事の仕方、人との接し方、その他生活習慣や余暇の過ごし方、またはファッションまで、強いられたり、気付いたり、いつの間にかそうなっていたり、環境の変化に対応すべく考えついた事であったり、私たちは今、様々な変化の瞬間を生きているといっても良いでしょう。Cisei というブランドを通して、その小さな過去を振り返った時、実はとても変化の少ない時間を過ごしていたことに気づきました。新作の考案から、業者様の為の展示会、受注を頂き生産する、というルーティーンをこなす事に追われ、いろいろな事を見落としたり、後回しにしていたかと思います。15年前とは比べものにならない程発達した、インターネット環境を礎とするEコマースなどの新ビジネススタイル、SNSなどを通し多くの人との間で縮まる距離感や容易な発信力の可能性、海外にいながらのコミュニュケーションも今ではほぼ無料にて快適に行うことができます。そんな現在に、改めてCiseiとしてするべきことを考えた結果、- お客様のもっと近くに- 実物の製品を手に取り見て欲しい- 定番だけでなく多くの品番を紹介したいなどが挙がり、それらの夢を叶える為、直営にてショールームを開設することにしました。今までの、職人、デザイナーと言った職種とはまた全く違うサービスにおいて、皆様にご満足いただける様、上手にこなせるかはとても不安ではありますが、是非お越し頂ければ、嬉しい次第です。少人数にて安心して時間をお過ごし頂けます様に、御来店は完全予約制とさせていただいております。お手数ではありますが、メールにてお問い合わせください。 Cisei Showroom2021年11月12日オープン 住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-22-1-2Fメールアドレス:showroom@cisei-firenze.com営業日時:月曜日~金曜日 12:00-20:00 (1時間刻みでのご案内となります) <ご利用前にお読み下さい>・予約制となりますので、ご来店希望日の3日前までに仮予約をお願いいたします。・仮予約の完了後、予約可否のご連絡をさせていただきます。 予約状況によっては、ご希望の日時でのご案内ができかねる場合がございますのでご了承ください。・本予約後、ご希望商品の確認をメールにてさせていただきます。・ご希望商品(オンラインサイトより商品の品番、お色を記載ください) 例)0901 LD BRIEFCASE COL.NAVY(T) ※注意:オンラインサイトで販売していない商品&ソールドアウトの商品はご用意出来かねます。担当:竹谷 ※メイドバイオーダーについてCisei + h(メイドバイオーダー)はデザイナーの大平が日本にいる際に受注会にてご案内いたします。受注会のご連絡はHPにてご案内いたします Cisei + h ショールーム開設に合わせ、メイドバイオーダーの新ラインを準備いたしました。私、大平の帰国時に、受注会を設けさせて頂きますので、お問い合わせください。量産品では使われていない素材や、製法を駆使し、自社工房内のみで作成いたします。通常のデザインをベースの商品から、+h 限定品番などを準備いたしています。ブランド名は本名の智生をイタリア語読みにした Cisei に本来のスペルに必要な h を足し、サイン通りに戻す事によって、職人としての物作りに対する気持ちを込めています。 大平智生 GALLERY ...